昨年の冬至の前に伊勢志摩を訪れた。
夜明け前の外宮、宇治橋で見た日の出、そして早朝の内宮。
いずれも素晴らしい時間だった。
その影響もあり、もう少し伊勢神宮、あるいは神社について知りたいと思っていたところ、年末に立ち寄った書店で手に取ったのが、この「<出雲>という思想 近代日本の抹殺された神々(原武史著、講談社学術文庫)」だった。
最近はどうしてもビジネス書や実用書ばかりを読んでおり、こうした学術書を読むのは久しぶりだったのだが、興味深く読むことができた。
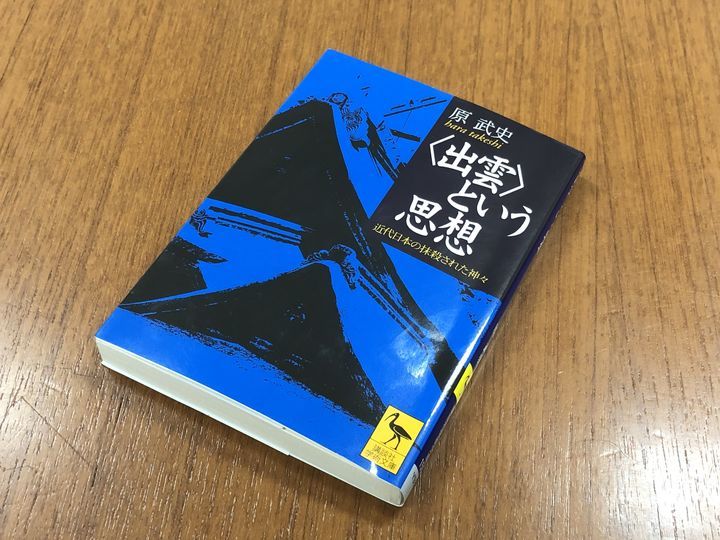
現在の皇族の祖とされる天照大御神を祀る伊勢神宮と、彼ら天津神に国を譲ったとされる大国主大神を祀るとされる出雲大社。
本書はその出雲信仰の歴史から紐解いていく。
ところで、出雲大社の祭神が正式にオホクニヌシとされたのは、明治に入ってからのことであり、それ以前は「出雲の神様」といえば、一般には「大黒さま」のことを指していた。大黒は七福神の一つで大黒天とも称し、サンスクリットのマハーカーラの意訳とされている。オホクニヌシの「大国」と「大黒」がともに音読みにすると「ダイコク」と読める語呂あわせから、室町時代以降、両者の同一化が急速に進んだ。人々は出雲大社には台所の神様、すなわち頭巾をかぶり、右手に小槌、左手に袋を背負い米俵の上に乗る福の神が鎮座し、家々を守護してくれていると考えるようになったわけである。
さらに江戸時代になると、十月を神無月と呼ぶのは全国の神々が出雲に集まっているからであり、そこでは各地の氏神の報告をもとに「彼是の配偶」が決定されるとする縁結びの信仰が加わり、大社といえば男女の縁をとりもつ神様のまします地というイメージもまた一般化していった。いずれにせよ、一般の日本人にとって、「出雲の神様」とは人々に利益や幸福をもたらす、きわめて現世的な神にほかならなかったといえよう。
<出雲>という思想 近代日本の抹殺された神々
原武史著、講談社学術文庫、p.45,46
しかし、こうした信仰を「近世の附会」としてしりぞけたのが、江戸時代に生きた国学者の本居宣長であると本書は説く。
その後、平田篤胤を経て、明治期の神学論争、そして出口王仁三郎らによる大本教に至るまでの思想史の変遷が、詳細に記されている。
しかしながら、紆余曲折を経た論争の末に、<出雲>は敗れた。
しかしながら、王仁三郎や折口のような例は、あくまで若干の例外にすぎない。戦後の神道界に君臨し、伊勢神宮を「本宗」として崇める神社本庁のある教科書では、王仁三郎の説は全く無視、戦後の折口の説は、篤胤の説とともに「異端」扱いになっている。
<出雲>が<伊勢>と相対立する思想的機軸となり得た日は、すでに遠い過去のものとなった。そしていまはただ、宣長が「近世の附会」として斥けたはずの民間信仰が、家内安全やよき人との出会いを求める人々の足を、出雲へ、大社へと向かわせているのである。
同上 p.213,214
その過程で成立した明治国家における「国体」「近代天皇制」の確立は、<伊勢>=国家神道の勝利であり、<出雲>はその陰で忘れられたもう一つの神道であったというのが、本書の骨子である。
=
読了して改めて思うのは、いま現在の伊勢神宮や出雲大社のかたち、あるいは信仰といったものはずっとそうだったわけではなく、長い歴史の中で培い、変遷していった上でのかたちである、という事実だ。
「伊勢神宮とは」「出雲大社とは」「国譲りの解釈とは」といったことが、今から300年も昔の江戸時代から議論されてきたのだ。
どうしても私たちは、いま存在している形がずっとそのままあったように感じてしまうが、あくまでそれは様々な歴史の織りなりの結果に過ぎない。
いまの伊勢神宮や出雲大社の形そのものが、本書に記されているような思想史の衝突や変遷を経て、その形になっているというのは、考えてみれば当たり前の話なのだが、改めて先人たちの言葉を引きながらそれを知ることができたのは、非常に興味深かった。
=
さて、そうした<伊勢>と<出雲>をめぐる思想史の変遷は、知識としてあれど。
伊勢神宮を訪れた際の、あの「感じ」は何なのだろう、と思う。
長い時間をかけて、途方もない数の人たちが訪れ、手を合わせてきた「祈り」の蓄積なのだろうか。
こう書いてしまうと、学術的な本書の書評としては相応しくないのかもしれないが。
それでも、
あの参道を歩いているときの、肌感覚。
あの感覚は、私を魅了して止まない。
いつか、<出雲>の地も訪れてみようと思う。