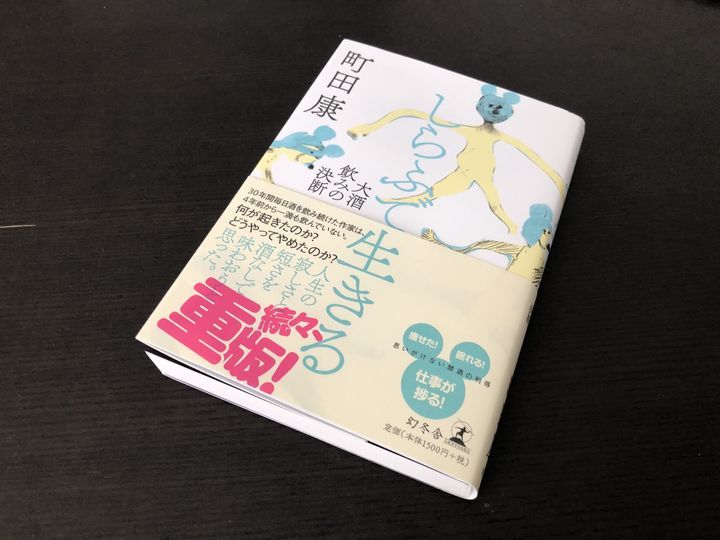久しぶりに書評を。
町田康さんの著書「しらふで生きる 大酒飲みの決断」(幻冬舎刊/以下、本書と記す)に寄せて。
タイトルそのままの通り、「飲みに飲んで、差されれば必ず受け、差されなくても手酌で飲んで斗酒をなお辞さない生活を三十年間にわたって続けた(本書p.8)」著者が、ある日突然、禁酒をした経験談についての本である。
三十年間とまではいかないし、大して強くもなかったので斗酒までは飲めなかったのだが、私も二十年近く「差されれば必ず受け、差されなくても手酌で飲んで」きたが、その飲酒を1年半前に突然辞めたクチである。
この本は、私のそのような経緯をご存じの、たいせつな知人の方から紹介をいただいたのだが、本書に記されている著者の心境、考察、こころの機微については、首がちぎれんくらいに頷かされるばかりであった。
もしかしたら、それまで浴びるように飲んでいたのに、ある日突然禁酒したくなる…そのような経験をした人にとっては、同じように共感できるのかもしれない。
そのような経験をしたことのある人が、どれくらいいるのか分からないが。
=
おそらく、そのような「ある日突然、酒がやめたくなる」人は、「酔うためにお酒を飲む」人なのではないかと思う。
以前にここでも書いたような記憶があるが、お酒が好きな人には二種類あって、「お酒の味や香りが好きな人」と「お酒がもたらしてくれる酩酊感や賑やかな場が好きな人」がいる。
そして、著者も私も後者であるように思う。
本書のなかに、お酒の味についての記述が一度も出てこないのが、その象徴である。
お酒の味や香りといったものが好きな人たちは、こうした「突然酒がやめたくなる」という心境にいたることは、あまりないのではないかと思う。
ところが、「酔うために飲んでいる」人たちにおいては、ある日突然「その日」が訪れることがある。
それは、「酔うことで得られていた何か」が、自分の中で必要でなくなった時なのかもしれない。
それが、自覚的であれ、無意識的であれ。
「あ、酒、やめてみよう」
そういう心の奥底から響いてくる声を聴く瞬間が、あるのだ。
著者は、その瞬間を狂気として表現しておられる。
つまり酒を断つこと、というか自分がそんなおかしなことをしているということを認めたくなかったので、いままで意図的にこの言葉を使わないできたが、使ってしまおう、禁酒・断酒というのは常に自分のなかの正気と狂気のせめぎあいであって、飲みたい、という正気と飲まないという狂気の血みどろの闘いこそが禁酒・断酒なのである。
(本書 p.27)
まさに、である。
いままでの正気と、ふと生じてしまった狂気の声との闘い、それが断酒なのかもしれない。
それでも、「酔うこと」を必要としなくなった理由を、もっともらしく説明することもできよう。
私の場合は元来、大容量で抱えていた「寂しさ」を忘れるために飲んでいたが、それが癒されるにつれて、「酔うために飲む」ことが必要なくなった。
あるいは、著者の場合は「自分は幸福になれるはずなのに」という渇望感から飲んでいたが、「そもそも人生は楽しいものではない」という達観に至り、「酔うために飲む」ことが必要なくなったのかもしれない。
それでも、やはりしっくりくるのは「狂気」という説明なのだろうと感じる。
それは、古い自分からの脱却と言い換えてもいいのかもしれない。
=
最後に著者は断酒についてのメリットを述べておられる。
そこでここまでの禁酒による利得を整理すると、
①ダイエット効果
②睡眠の質の向上
③経済的な利得
でありいずれも素晴らしき利得であると言えるが、禁酒の利得はこれにとどまらないので、さらに申し上げると前に少し言った、脳髄のええ感じ、というのがある。
どういうことかというと、これは仕事をしているとき、或いは、なにかについて考えているときに実感するのだが、酒を飲んでいたときに比べて考えるひとつびとつのことが聯関するというか、ひとつのことの、また別の一面に気がつく、といったことが脳髄において起こり始めた。
(本書 p.203.204)
これまで何度かここで書いてきたとおり、私もそのメリットについては完全に同意する。
特に、あまり語られることのない「④脳髄のええ感じによる仕事の捗り」については、本当にそうだと感じる。
そして、もう一つ、最後に書かれた利得についても、本当にそうだと頷くばかりである。
少し長いが、私が断酒で得られた最大の利得を、これほどうまく言語化されていることに驚きを禁じ得なかったので、引用させて頂きたい。
そんななか稍抽象的で分かりにくいかもしれないと考えて書かなかったことがある。
というのは、精神的ゆとり、ということである。ゆとりという言葉には今は悪い印象がある。別の言葉で言うと、余裕・余白ほどの意味である。遊び、と言ってもよいかもしれない。これまではそうた余裕・余白がなかったため、強い刺激、という目的に高速且つ最短で向かっていたのだが、余裕・余白が生じ、ゆっくりと時に立ち止まりながら歩むことができるようになった。
そうすることに以外のよろこびや驚きがあることを知った。それは草が生えたとか、雨の匂いとか、人のふとした表情のなかにある愛や哀しみといった小さなものである。急いで通り過ぎると見落とし、見過ごすようなものである。けれどもそれこそが幸福であるということをやっと知ったのであった。
ではなぜそのような余白が生じたのであろうか。それはこれまでは目的地を、楽しみ、と誤って設定し、急いでいたが、本当はそれが、死、であることを知り、死を恐れる気持ちから急ぎたくなくなり、また、何もない瞬間を大事に思いたい、という心境に至ったからであろう。強烈な刺激の中ではそのような心境には至らない。
(本書 P,213,214)
これは、先に述べた著者の「そもそも人生は楽しいものではないという達観」と表裏をなすものであると思う。
そもそも幸福とか快とか思っているものは、本当は「死」なのかもしれない。
強い酩酊や刺激がなくても、大丈夫なのだ。
そして、いまあるこの何気ない瞬間を大切に愛おしく感じること。
それが、本当のところ、わたしや著者が求めていたものなのかもしれない。
そう思わせてくれる、一冊だった。